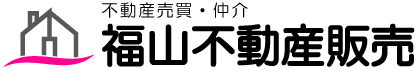お役立ち情報– category –
-

【福山 不動産】土地の傾斜(勾配)を測る簡単な方法
スマホの水平器アプリで失敗しない土地チェック術 福山市で不動産を探していると、「この土地、ちょっと傾いてない?」「なんとなく坂っぽいけど、大丈夫かな…」と感じたことはありませんか? 土地探しで意外と見落とされがちなのが、土地の傾斜(勾配)で... -

【福山版】実家の売却「空き家バンク」と「一般仲介」はどちらが正解? 成功のための徹底比較
福山市内に実家があり、相続や介護をきっかけに売却を検討される方が増えています。しかし、いざ売るとなると、不動産会社に頼む「一般仲介」だけでなく、市が運営する「福山市空き家バンク」という選択肢もあり、「どちらがいいのか?」と迷われるケース... -

福山市の「立地適正化計画」と土地売却:居住誘導区域外の土地を早期売却すべき理由
福山市で土地を所有している方にとって、今もっとも知っておくべき行政用語、それが「立地適正化計画」です。 「先祖代々の土地だから、持っていればいつか価値が上がるだろう」 「福山駅周辺が再開発されているから、市内全域の地価も安泰だ」 もしそう考... -

神辺エリアの土地売却:市街化調整区域の「農地転用」で宅地化して売るための具体的ハードルと戦略
福山市の中でも、神辺町は非常に特殊なエリアです。「フジグラン神辺」や「フレスポ神辺」周辺の目覚ましい発展がある一方で、一歩道を挟むと広大な田畑が広がり、その多くが「市街化調整区域」に指定されています。 「親から継いだ神辺の田んぼを売って、... -

「相続放棄 vs 売却」福山市の山林・傾斜地を相続した際の維持コストと手放し方:完全ガイド
福山市にお住まいの方、あるいは遠方に住みながら福山市内に「負動産(山林や傾斜地)」を相続した方にとって、その土地をどう扱うかは人生を左右する大きな問題です。 「親が持っていた神辺町の裏山、どうすればいい?」「鞆の浦が見える斜面地、景色はい... -
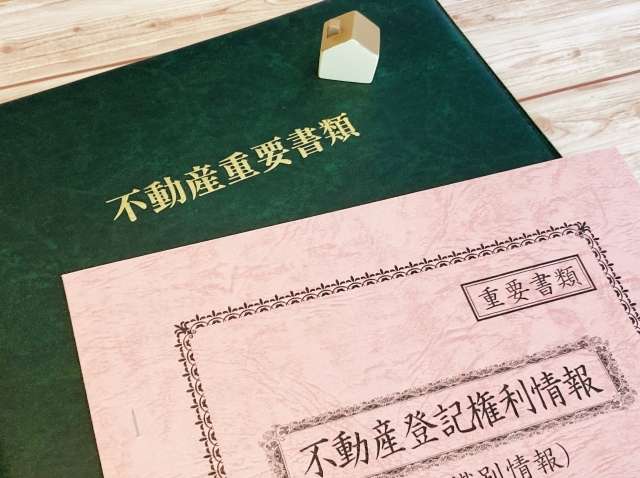
不動産取引の重要知識:公簿面積と実測面積の違いとは?福山市での土地選びのコツ
福山市で不動産売却や購入を検討されている皆様、こんにちは。 「いざ土地を売ろう!」あるいは「マイホームのために土地を買おう!」と登記簿(登記事項証明書)を確認した際、「実際の広さと違う気がする……」と違和感を覚えたことはありませんか? 実は... -
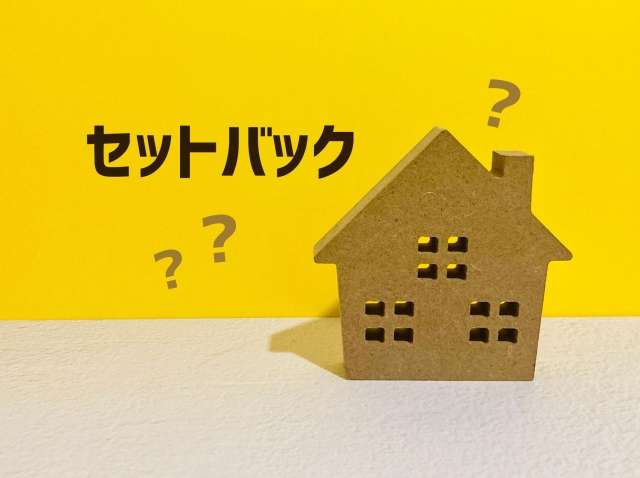
前面道路の「幅」と「種類」で何が変わる?:建築基準法上の道路(4m以上)の確認ポイント
はじめに:福山で不動産を探すあなたへ!道路の重要性とは? 福山エリアで一戸建てや土地の購入を検討されている皆さん、物件探しで間取りや日当たり、周辺環境を重視するのは当然のことです。しかし、実はその物件が面している「前面道路」が、その土地の... -

「地盤」って何を見ればいいの?地盤調査報告書(ボーリングデータ)の簡単チェックガイド
はじめに:地盤って、正直よくわからなくない? 「マイホームを買う!」って、ワクワクするけど、実は不安なこともいっぱい。予算、間取り、デザイン…そして、一番見落としがちで、でも超重要なのが「地盤」です。 特に、これから家族や自分の資産を守って... -

中古物件購入「手付金」ってそもそも何? 契約解除で戻ってくるのはどんな時?
はじめに:手付金を知って、福山での物件購入を成功させよう! 「将来は福山でマイホームを持ちたいな」「そろそろ中古マンションを探し始めようかな」と考えている皆さん、こんにちは! 物件探しってワクワクする一方で、「不動産用語が難しすぎる…」と感... -

福山で最高の物件を見つけるための「日当たりチェック」完全ガイド!
この記事は、福山エリアで初めてのお部屋探しや物件購入を考えているあなたに向けて、「日当たりのチェック」に徹底的にフォーカスしたお役立ち情報をお届けします。 「おしゃれな物件を見つけたけど、実際住んだら暗かった…」なんて失敗はしたくないです... -

【DIY?業者?】古いドアの「きしみ音」や「立て付けの悪さ」はどこまで直せる?賃貸・購入のマル秘テク!
はじめに:その「ギィーッ」に、もう悩まない! 福山でお部屋を探している皆さん、こんにちは! 築年数がちょっと経った、魅力的な賃貸物件や中古マンションを見つけたとき、ひとつ気になるのが「設備の古さ」ですよね。 特に、毎日の生活で必ず触れる「ド... -

【福山 不動産購入ガイド】残置物、そのまま引き取るべき?賢い交渉術と廃棄費用のリアル
はじめに:マイホーム購入で意外と見落としがちな「残置物」のリアル 福山市内で初めてマイホームを購入しようと考えている皆さん、おめでとうございます!夢の実現に向けてワクワクしていることでしょう。 物件探しやローンのことで頭がいっぱいになりが...